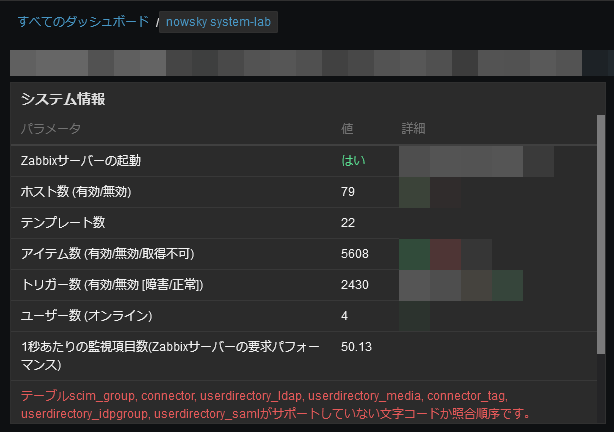2023年08月05日(土) - 12:45 | カテゴリ:
Linux
オープンソースのRDBMSと言ったら、MySQLとMariaDBを思い浮かべる人は多いと思う。
筆者も同じタチで、しかも作る物が殆どMySQLかMariaDBを前提にしているのもあり、
動作互換性のチェックの為にも両方の環境を維持する必要があった。
そんな中、”ns-lab BB”バックボーン用Web鯖のApacheをアップグレードしようと、
APR-utilにmakeを打ち込んでみたら「my_boolなんて存在しない」と怒られた。
エラー文のコピーを忘れてしまったが、my_bool型を参照しようとしてエラーになっていた。
………
MySQL 8.0より古いバージョンではmy_boolを使っていたが、
MySQL 8.0以上では廃止されて普通のbool型を使うか、intで数値として取り扱う様に変わった。
APR-util 1.6.3がこの対応が出来ておらずエラーに繋がった。
- MySQL 8.0 C API Developer Guide [PDF]
MariaDBはmy_boolをサポートし続けているので普通にビルドが出来るのだが、
MySQLはサポートを打ち切った影響で今回のエラーが出てしまった形となる。
修正箇所はASF Bugzillaに上がっており、apr_dbd_mysql.cでbool型にtypedefすれば良い。
MySQLのドキュメントでも今後はboolを使う用に記述がある位なので、
typedefで別名つけても普通に動く。
MySQLからMariaDBに切り替えるのも手だが、
筆者の様に必要な環境もあるので、久々にAPR-utilをアップグレードしてくれたら嬉しい限り。
2023年07月21日(金) - 22:27 | カテゴリ:
Linux
“ns-lab BB”のサーバ管理にAnsibleを多用しているのは言うまでもないが、
サーバをメンテナンスするタイミングを逃して実行環境を放置していた。
昨日、メンテナンスの時間を確保出来たので、
KVMホストのメンテと一緒にAnsible実行環境のアップグレードしたのだが、
Ansible 2.14.2へ変わったのがマズかった。
一部のプレイブックでは以前作成した管理用スクリプトをshellモジュール経由で叩く様にしており、
その中で警告メッセージを減らす為にshell:warnの設定を入れていた。
しかし、Ansible 2.14でshell:warnが削除されたのでエラーで失敗する様になった。
Starting in 2.14, shell and command modules will no longer have the option
to warn and suggest modules in lieu of commands.
The warn parameter to these modules is now deprecated and defaults to False.
Similarly, the COMMAND_WARNINGS configuration option is also deprecated and defaults to False.
These will be removed and their presence will become an error in 2.14.
|
コレに気づかず、アップデート後初のAnsible実行でエラーの嵐が発生。
普段動いていた物が動かなくなったので焦ったが、独自に組んでいたログ取得からデバッグを開始。
表題の通り、shell:warnの所で処理が軒並み停止する事がわかった。
Ansibleの更新履歴を追いかけた所、v2.11のDeprecatedリストにそのまま載っていた。
実行時もwarnオプションが存在しないから削除する様にエラーが出ていたので予想はついていたが、
更新履歴はちゃんと読まないとハマる事があると改めて実感した出来事だった。
………
自宅鯖だからこそ読まずにぶっつけ本番をした結果ハマった原因だが、
流石に自宅鯖で全部追いかけるのは大変なのと、
趣味の範疇だからこそぶっつけ本番チャレンジ出来るのがメリットなので、
敢えてやり方は変えず今回の事も備忘録にしておこうと思う。
2023年03月27日(月) - 21:30 | カテゴリ:
Linux
zabbixの追いかけを放置してProxmoxに浮気している間に6.4がリリースされていた。
最新版が出たとなるとアップグレードして動作を見ておきたいのと、
ついでにバックエンドのMariaDBも同時にメンテを行ってみた。
データベースの方は、MariaDB 10.7からMariaDB 10.11へアップグレードをした。
zabbix 6.4はMaria DB 10.11に対応していないが、
次期マイナーバージョンでは対応予定にもなっているのでLTS適用を優先した。
DBのフルダンプを事前に取得してデータが壊れても復旧出来る様にしてから着手したが、
“mariadb-upgrade”も全てPASSして作業が完了した。
下記の公式マニュアルを事前確認しておいたのも効いた。
………
zabbixの方はZabbix ServerとZabbix Proxyを停止してからバイナリを入れ替えつつ再起動。
コンフィグは一文字も変更せず流用したが無事に起動した。
が、データベースの文字コードと照合順序が古いままだったのと、
主キーが古いままだった事に気づいたので修正も実施。
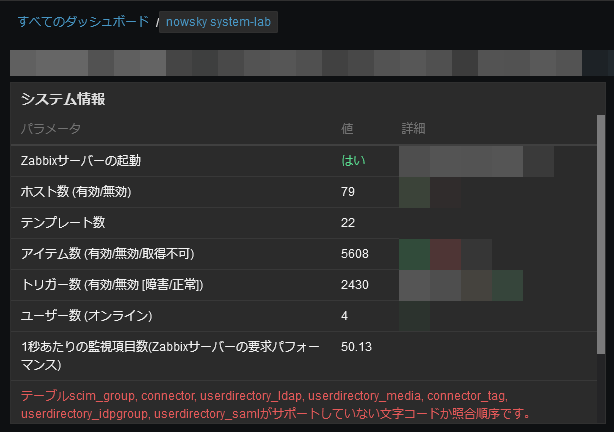
zabbixを長年動かし続けると遭遇する事が多いデータベース絡みのエラー。
毎回手動で直すのも面倒なので、今回はデータベース自体の照合順序も変更した。
主キー更新はオンラインドキュメントの手順に従い実施したら終わったので割愛。
そんなこんなで文字コード照合順序打ち込んだコマンドは次の通り。
厳密には、もっと丁寧に実施した方が良いが自宅サーバなので手抜きした。
データベース名は”zabbix”に置換しているが大体のコマンドは合っている。
SELECT SCHEMA_NAME,DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME,DEFAULT_COLLATION_NAME \
FROM information_schema.schemata \
WHERE SCHEMA_NAME = 'zabbix';
+--------------------+----------------------------+------------------------+
| SCHEMA_NAME | DEFAULT_CHARACTER_SET_NAME | DEFAULT_COLLATION_NAME |
+--------------------+----------------------------+------------------------+
| zabbix | utf8mb3 | utf8mb3_general_ci |
+--------------------+----------------------------+------------------------+
SELECT TABLE_SCHEMA,TABLE_NAME,TABLE_COLLATION \
FROM information_schema.tables \
WHERE TABLE_SCHEMA = 'zabbix' AND TABLE_COLLATION = 'utf8mb3_general_ci';
+--------------+------------------------+--------------------+
| TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_COLLATION |
+--------------+------------------------+--------------------+
| zabbix | scim_group | utf8mb3_general_ci |
| zabbix | connector | utf8mb3_general_ci |
| zabbix | userdirectory_saml | utf8mb3_general_ci |
| zabbix | userdirectory_ldap | utf8mb3_general_ci |
| zabbix | userdirectory_media | utf8mb3_general_ci |
| zabbix | userdirectory_idpgroup | utf8mb3_general_ci |
| zabbix | connector_tag | utf8mb3_general_ci |
+--------------+------------------------+--------------------+
ALTER TABLE zabbix.scim_group CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
ALTER TABLE zabbix.connector CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
ALTER TABLE zabbix.userdirectory_saml CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
ALTER TABLE zabbix.userdirectory_ldap CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
ALTER TABLE zabbix.userdirectory_media CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
ALTER TABLE zabbix.userdirectory_idpgroup CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
ALTER TABLE zabbix.connector_tag CONVERT TO CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
ALTER DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_bin;
|
データベースを弄った後にZabbix ServerとZabbix Proxyを再起動して10分程度動かすと反映される。
………
実際にzabbix 6.4を弄ってみたが目に見えて大きな変更点が無くすんなり弄れた。
公式サイトに書いてある、テンプレートをバージョン管理出来るっぽいのが便利に見えたが、
手動で管理する物では無さそうだった。
zabbix 5.0の時にあったUI変更の様に目に見えた大きな変更点は無かったので、
エンタープライズ用途でも学習コストが少ないのは嬉しい。
その割には内部処理は高速化されているみたいなので暫く動かしてみる。
今回の6.4へのアップグレードはすんなり出来た。
二の足踏んでいる自宅サーバ民ならサクッと実施しても大丈夫だろう。
« 続きを隠す