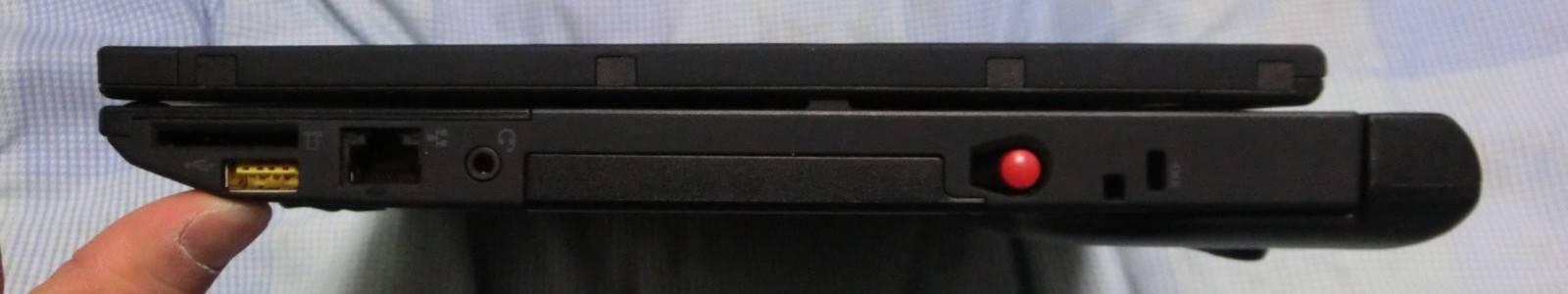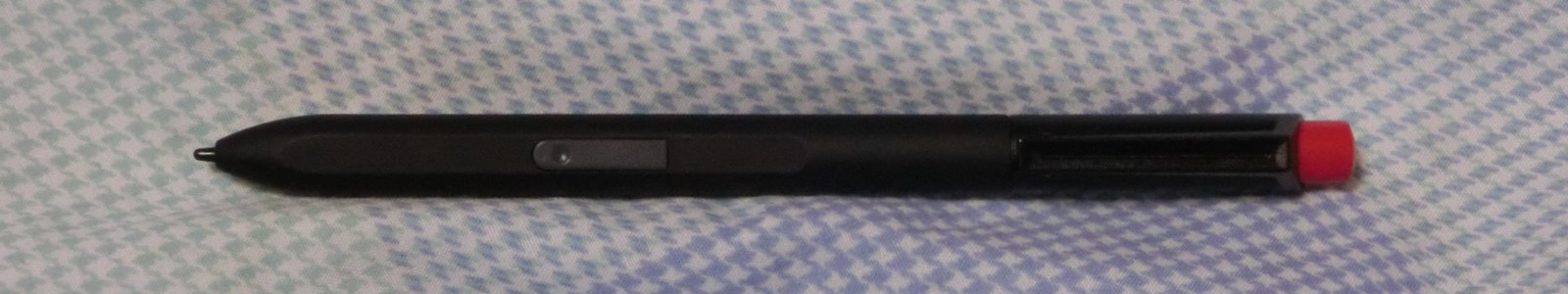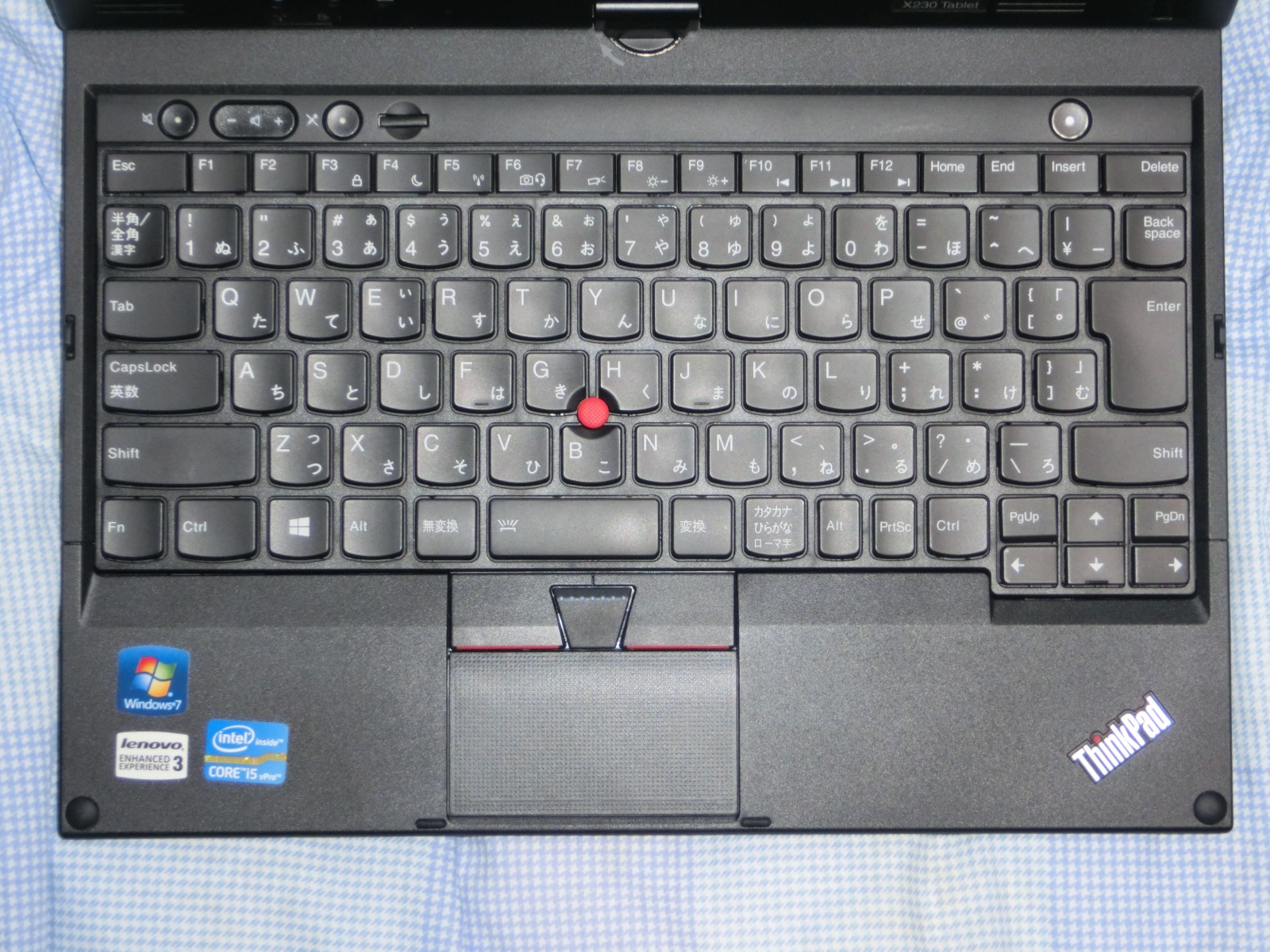DigiLoogのデータ領域をNFSに切り出してみた
今年やりたい事の一つとして挙げていた、自鯖のSSL対応をする為に
自鯖構成を大きく変更し続けている昨今。
その中の一つとして、拠点内・外冗長化対応も(実は)含んでいた為、
データ領域をどうやって冗長化するかが課題になっていた。
GlusterFSのレプリカ構成や、lsync+rsyncによるdaemon同期、
仮想環境レベルのデータ共有マウントなど色々な方法が候補になり、
テストをした結果を踏まえて、今回はNFS共有マウントという構成を採用する事とした。
最後まで候補に残っていたGlusterFS、NFSについてはベンチも取ったので、
次回のブログ更新時にちゃんと記事を起こす予定。
ちなみに、この記事は出先から書いているので、そもそもデータが手元に無かったり (´;ω;`)
大きな変化としては、ローカル読み込みが10MByte/s出ていたのが、
NFSに切り替えた事で、3MByte/sまで落ちた事。
さすがに、ローカルといえどもギガビット回線がローカルマウントに勝つ事は出来なかった (´・ω・`)
ただ、今のところはユーザが実感できるレベルで遅延は起きていない模様。
細かいベンチはサーバ冗長化・リバプロ負荷分散の最終構成まで組んでから実施してみようと思う。